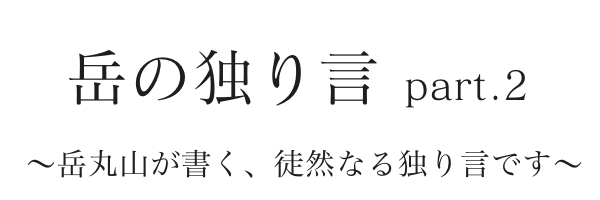<ある展示会での出会い>
2015年、16年の2年間、先日ご逝去された医師日野原重明先生が名誉医院長をお勤めになっていた都内の某病院で写真展を開催した。きっかけは、友人が難病でその病院に入院されていたある読者から「友達を励ます為に写真展を開催して欲しい」との連絡を戴いたからである。
私は2003年に持病の心臓病が悪化し、計らずも死の受容に伴う魂の痛みを経験した。幸い名医と巡り会い奇跡的に手術は成功し一命を取り留めた。退院の朝、ある決心をした。「自分が体験したような苦悩の中に今現在いる多くの人々に、少しでも癒しを与える何かが出来たなら・・・」その想いが原動力となり、10年前から緩和ケア施設を併設する病院を中心に富士山写真展を開催してきた。
難病で入院中だったそのご友人には、2016年の2回目の写真展でお目にかかり写真も鑑賞して戴いたが、残念ながら翌2017年にお亡くなりになられた。さぞかし無念であったことだろう・・・ ご冥福を心からお祈りしたい。
これから話す出来事は、その2回目の展示会でのエピソードである。
私は展示会を開催する度、写真をご覧戴いた患者さんの感想をお聞きしたく、小さなノートを受付けに置いた。また重篤な患者さんが入院されている医療施設を中心に、写真展を開催し続ける私なりの理由を、挨拶状としてしたため、希望者に配布していた。
今回の病院の展示ギャラリーは緩和ケア治療室に向かう長い廊下の一部であった。ギャラリースペースの奥には荘厳なチャペルがあり、その空間と静寂さは、いつでも自分自身を見つめ直す時間を、差別なく万人に与えていた。
開催日2日目、ご病気の様子の女性の乗った車椅子を、ご主人らしき男性が押し、長い廊下を渡り会場にやって来た。暫くの間、二人で興味深そうに写真を鑑賞してから、隣の外来緩和ケア室に移動された。数十分経過した頃であろうか、診察を終えた様子で再来され、再びゆっくりと写真を鑑賞された。帰り際、私が撮影者である事に気付いた様子で、車椅子のご婦人からサインを所望された。サインは婦人の手の平に、同時に婦人の名前を書いて欲しいと言われた。名前は「のぞみ」だった。私は「希」か「望」のどちらか迷ったが「希さんへ」と書いた。それを見た婦人は、何か言いたそうな顔つきであったが何も言わず、礼を告げてその日は帰られた。
次の日の午後、車椅子のご婦人は再度診察にやって来た。昨日の通り外来緩和ケア室に向う途中、写真を見に寄ってくれたのだ。暫く鑑賞した後、ご婦人がもう一度手の平にサインを書いて欲しいと、昨日とは反対側の手を広げられた。「こんどは「望」と書いて下さい・・」と少し遠慮がちに言った。
「昨日、本当の名前は「望」だったけれど、間違っていても構わないと考えました。今日もう一度「望」と書いて貰えれば「希」と合わせて「希望」になると思ったから・・・」と話された。
差し出された手の平は痩せ細り、通院も大変な苦労をされながらの事であろうと容易に想像出来た。最後に握手した手も弱々しく、終末期の患者さんである事は容易に推察された。その魂の痛みを必死に受け止めている様子に、思わず込み上げてくるものがあったが、指先から「負けるな!」「負けるな!」と、想いを婦人に届けた。
展示会の最終日、付き添いもなく一人の患者さんが車椅子の車輪を回しながら来場され、長時間写真を熱心にご覧になっていた。50歳前後の品の良いご婦人であった。きっと緩和ケア治療室で治療が終わり、病室に戻る途中で気付いてくれたのだろう。気配を伺いながら興味深そうな写真数点を解説させて戴き、その後、挨拶をして別れた。しかし直ぐにテーブルに置いた挨拶状を持たずに帰られたことに気付いた私は、廊下のスロープの途中にさしかかったご婦人を追いかけ、車椅子を背後から押しながら挨拶状を手渡した。軽く会釈するとご婦人は、その場に車椅子を止めたまま、真剣な目付きで挨拶文を読み始めた。私はすぐにその場を離れたが、遠目で見ても繰り返しくりかえし、何度も読んでいる様子が見てとれた。10分近く経ったであろうか、その光景に突然私の目頭が熱くなった。それは13年前、まさに苦悩の最中、もがき苦しんでいた自分自身の姿を、その婦人の中に垣間見たからだ。
死の受容という究極の苦しみは、生涯何回も体験することではない。しかし、その唐突さと折り合いのつけ方の難しさに、人は右往左往し思い悩む。きっとそのご婦人も、自分自身がこの世から居なくなってしまう事に対する答えを、自らに言い聞かせる為の僅かなきっかけや助けを、何かに求め続けてきたに違いない。それはその後ろ姿から容易に推察することが出来た。魂の痛みと闘う患者さんにとって言葉は余り意味を持たない。人は何に属し、何処から来て何処へ帰って行くかを理解する過程の中に「生命の真理」に気付く瞬間が隠されているような気がする。私の言葉に力はないけれど、ただ真実の体験を伝えようと挨拶文を書き続けてきた。
「私の体験が少しでもお役に立てたなら・・・」いつもそう願ってきた。
展示会が終了してから数日して病院の開催責任者から次のようなメールが届いた。「会場の整理をしていたところ、一枚の手紙が会場入口のパンフレット置き場に置かれていたので、写真に撮りメールで送ります」とのことだった。
以下が送られてきた文面である。
「奇跡の人生から生まれた奇跡の癒しの写真。大自然の中に生かされている私達一人一人、感動と共に感謝して、ひとときひとときを生かされてゆきたいと思いました。ありがとうございました。」
文章を読み終わり、きっとあのご婦人からであるに違いないと咄嗟に確信した。届くかどうか分からない手紙を、病院に託してくれたのだ。
写真展の度にいつも想う。「たったひとりでいい・・・何かが伝われば・・・」
そして、富士山は日本人の心に響く山であることを。